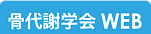

【ソクラテスの書棚】朝井まかて作「眩」
「この世は、円と線でできている。
眠りこけてる猫なんぞ尻と背中、それから頭もだ。
ほれ。こうして、円が重なってるだろう。」
(「眩」より)
お栄は、父のことを「親父どの」と呼ぶ。幼い頃から、父の周りに集う弟子や版元が父をそう呼んでいたからだ。父の胡座の上に座り、父の手の中の絵筆が生み出す世界を見続けてきた。紙の上に描かれた猫は、たちまち両の耳を立て、顔を上げ、あくびを漏らして前足を踏ん張った。それが不思議で、お栄はただただ無心に絵筆へと手を伸ばしていた…。
父娘の対話から始まる本作は、江戸の浮世絵師・葛飾北斎の娘であり、「江戸のレンブラント」と称される女絵師、葛飾応為の生涯を綴ったフィクション時代小説である。応為は画号であり、日常的にはお栄と呼ばれていた。物心がついた頃から父の工房に入り浸り、親父どのの絵に埋もれ、気がつけば他の弟子と肩を並べて修行していた。南沢等明という三流絵師に嫁ぎはしたが、その稚拙な画力と貧困な人間性に愛想を尽かして離縁。出戻ったお栄は父と起居を共にして浮世絵から風景画、さらには春画や枕絵までも生み出していたという。
親父どのとお栄は、貧乏と共に生きていた。北斎の名声は江戸中に知れ渡っていたが、当の本人たちは衣食の贅などに頓着せず、掃き溜めのような工房でひたすら絵筆を握っていた。お栄の腹違いの姉が産み落とした甥っ子は、北斎の名を利用して悪さを行い、借金の証文ばかりを生み出してくる。「我が孫なる悪魔」と言って親父どのが嘆く声に心底共感しながらも、ひとたび絵筆を握れば全ての浮世事は消え去って、絵の世界に命を燃やす。お栄は親父どのの落款で数多くの作品を生み出し、それを売って生計を立て続けた。
「女子栄女、画を善す、父に従いて今専ら絵師となす、名手なり」
(「眩」より)
北斎宅に出入りしていた浮世絵師・渓斎英泉は、お栄のことを自著でそう称している。本書の中でも英泉は「お前ぇはほんと、己の腕をわかってねぇんだ。呆れるほど」と言って、お栄に自身の名で勝負することを促していた。英泉の言葉を胸に、お栄は夜の闇と光を描きはじめた。「夜の闇の中でも、いくつもの光と影がある。何のどこを真の闇に沈め、何を光で浮かび上がらせるか」。そうして生まれた肉筆画は、眩々するほどの輝きを放つものとなった。葛飾北斎という偉大な絵師とともに生き、同時に自身の世界を追い求めた女性の一生が、本書の中に奔放に詰め込まれていた。
葛飾応為の落款が入った作品として確認されているのは、世界中でもわずか10点ほどと言われている。本書の表紙を飾る肉筆画の「吉原格子先之図」は、東京の太田記念美術館に所蔵されている。三人の女性が琴、三味線、胡弓を演奏する肉筆画「三曲合奏図」は米国のボストン美術館に、毒矢を受けた関羽が血を滴らせる場面を描いた肉筆画「関羽割臂図」は米国のクリーブランド美術館に、また夜の闇の中に佇む美女を描いた肉筆画「夜桜美人図」は、愛知のメナード美術館に眠っている。
本書を読み終えたその日に、思わず太田記念美術館に駆けつけてしまった。しかしその時は別の展示会が開催されていて、吉原の夜景に出会うことはできなかった。そしてつい先日も、「夜桜美人図」を一目見ようとメナード美術館に遠征したが、一般公開は2週間後と言われ、こちらも見事に振られてしまった。高嶺の花は容易く手には入らないということなのか。多少の落胆は感じたが、同時に「いつか葛飾応為の作品を全て制覇してやる」という野望がふつふつと湧き上がってきた。
偉大な親を持った娘は、それに奢ることなく、卑下することなく、父の名の影に自分が隠れてしまうことを嘆く間もなく、ひたすら自分の絵の世界を追い求めていた。「死んじまうその刹那まで、生き抜こうじゃないか」。きっとお栄は、満足した人生を送ったのだと思う。そんな生き方もあるのだと、本書を読んで眩しく思った。私も、そんな生き方をしてみたい。

