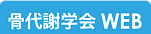

【ソクラテスの書棚】垣根涼介作「室町無頼」
― 自分の武器を持て。 垣根涼介
その本を広げた瞬間、そう書き殴られた銀色の文字が目に飛び込んできた。それまでサイン本というものに魅力を感じたことはなかったが、書店で「室町無頼」という名のサイン本を発見して、思わず衝動買いをしてしまった。著者の垣根涼介の力強い肉筆を見て、一気に魂を掴まれてしまったのだ。
寛正二年(1461年)、京の都は室町幕府の統治下にあった。第八代将軍・足利義政は文化人として名高い一方で、政事は母や乳母、側近たちの意のままに操られる傀儡政治となっていた。加えて、長禄三年(1459年)から足かけ三年続いている長禄寛正の飢饉によって、四条河原は餓死者の骸で埋め尽くされ、高い租税に各地で土一揆が頻発し、人の命は馬糞同様に軽いものとなっていた。
「現世に 神も仏も あるものか ――」
(「室町無頼」より)
17歳になる才蔵は、そんな乱世の中をただ一人で生きていた。洛中で物売りとして生計を立て、追い剥ぎや盗賊には天秤棒を武器に対抗する。その腕を見込まれて用心棒として雇われることになったが、ある晩、護衛していた土倉に賊が押し込んできた。味方が無残に斬り捨てられる中、才蔵は一人応戦する。しかし目の前に現れた偉丈夫の大入道は、桁違いの技量で才蔵を討ちつけた。
賊のアジトで目を覚ました才蔵に、大入道は自身の名を告げた。骨皮道賢、洛中一の悪党の親玉であり京洛の治安部隊をも担う男は、才蔵の命を奪うかわりに才蔵の身を牢人の蓮田兵衛に預けると言う。引き会わされた兵衛は、優男のような見かけとは裏腹に、尋常ならざる剣技を有し、道賢と同質の秘めた何かを抱いていた。兵衛は才蔵に兵法者としての修行を与え、才蔵は血の滲むような修行の中で心身の技量を高めていく。そして、無類の強さを携えた男たちは、歴史に名を刻む企てに向けて乱世の都を駆け抜けていく――。
本書を読み終えた時、私は安堵の息をついていた。室町時代の京都から現代の東京に舞い戻り、自分はなんと平和な世界で生きているのだと感じた。室町の鴨川には人の骸が浮かんでいたが、現代の隅田川には屋形船が浮かんでいる。人々は刀などを持つ必要もなく、対話や交渉で日々の問題を解決している。現代は室町のような乱世ではない。「乱世」ではないはずだが、しかし果たして本当にそうだと言い切れるのだろうか?
著者の垣根氏にとって、本書は2冊目の歴史小説となる。私が初めて読んだ垣根氏の小説は「ヒートアイランド」という渋谷のストリートギャングを描いたミステリー作品だった。ヤバい金に関わった仲間を救うため、ヘッドのアキが現金強奪犯と攻防する。渋谷に蔓延る大人の世界の深い闇、その中でアキは自らの知恵と友情と腕っぷしを武器に疾走していく。これはまさに「室町無頼」に通じる乱世の物語ではないだろうか。
改めて見直してみると、現代もまた平和の裏で多くの矛盾や不条理が存在していることに気がついた。世界中の各国で政治の混迷が報道され、経済は不安定な乱高下を繰り返し、インターネットでは目に見えない無法な言動が横行している。日本でも6人に1人の子供が貧困と言われ、独り暮らしの老人を狙った詐欺集団が跋扈する。「現世に 神も仏も あるものか ――」才蔵のこの想いは、私たちがいま直面している世界と変わらないものかもしれない。
だからこそ「自分の武器を持て」という垣根氏の言葉が、強く胸に響くのだろう。人が生きる世界はいつの時代でも乱世であり、誰もが自分の身を自分で守る術を持たなくてはいけない。では、私たちの武器とは何なのだろう? 子供は「可愛さ」を武器に大人の愛情と庇護を得ている。経営者は人望を武器に、科学者は観察力と分析力を駆使して、作家は想像力と創作力を基盤に、生きる道を切り開いている。知識、技術、経験や人脈、あるいは運。現代を生き抜くために、私たちはそんな様々な形の武器を獲得していかなくてはいけないのだ。
あなたの武器は何ですか?

