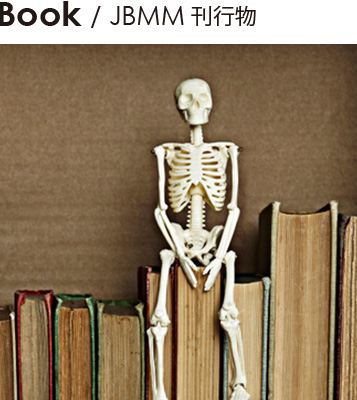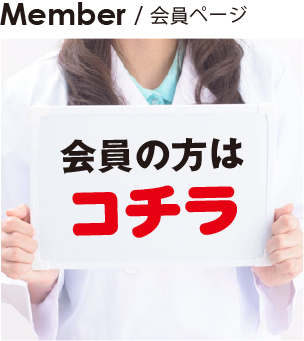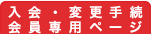
私の形態科学―“Beauty is truth, truth beauty”

すでに十数年前のことであるが最終講義で、形態科学の道を歩んできた私の好きな言葉として “Imagination is more important than knowledge in Science”(A.Einstain)、“Important discovery in Science and Technology are Serendipitous”そして”Beauty is truth, truth beauty“ をあげたことを思い出す。
特にジョン・キーツの 詩集“Ode on a Grecian Urn”(ギリシャの古壺のオード)の一節にある“Beauty is truth, truth beauty”「美は真なり、真は美なり」は、我が国の電子顕微鏡細胞生物学のパイオニアのお一人である山田英智先生の好まれた言葉でもある。この言葉は、対称性に美を求める数学の世界ではそのまま受け入れられるといわれるが、形態科学の世界でも「美は自動的に真を保障するわけではないが、その助けにはなる」ことは確かで、私の感性には素直に訴えてくる一節であり、今日に至るまで「私の形態科学」の支えになっている。柳 宗達は「自然は美の母」であるとも述べているが、自然の美を感じる感性こそが形態学の原点であり、たとえ分子レベルであってもそこに自然の持つ美が感じ取れる。
私が形態学の道を選んだのは、学生時代父から購入してもらった「一台の顕微鏡」と解剖学の講義で紹介された電子顕微鏡の世界、細胞微細形態の美しさであった。「一台の顕微鏡」については、かって学内誌に「記念すべきこと」として紹介したことがあったが、この「一台の顕微鏡」によって触発され、電子顕微鏡の極美の世界に魅入られ、卒業後直ちに当時我が国において新進気鋭の電子顕微鏡学者のお一人であった水平敏知教授の門を叩いた。以来、既に半世紀の歳月が流れた。
1931年、E.Ruskaによって倍率17倍の電子顕微鏡一号機が作成されて以来、近代科学史に残る20世紀最大のイノベーションの一つである電子顕微鏡は、0.1nm(1A)まで分解能が向上し、元素まで可視化できる顕微鏡として発展し現在に至っているが、わが国はその開発のトップを走り続けてきたことも私にとっては幸いであった。
私が研究を始めた時期は丁度、電子顕微鏡が医学・生物学分野に応用され始めた頃で、いかにして電子顕微鏡レベルで組織・細胞を観察するか、方法論の暗中模索に明けくれた。当時我が国では電子顕微鏡が漸く実用段階に入ろうとしていたころで、現在使用されている電子顕微鏡とは隔世の感があった。従って、最初の数年間は医学生物学に対応した電子顕微鏡のハードの開発とともに、その方法論・ソフトの開発にも多くの時間が費やされた。
水平教授は人真似を極度に嫌われ、「研究室では文献など読んではいけない。ひたすら手と頭を使って新しい科学を創造しなさい」と常に指導を受け、方法論の模索と創意工夫の日々が続いた。さらに得られた形態から何をイメージするか、形態科学におけるイマジネーションの重要性についてもしばしば触れられ「科学においてイマジネーションは知識より重要である」というアインシュタインの言葉を実感させられた。
当時、J.B.B.C(現J.C.B)、J.Ultrast.Rなどに毎号掲載された見事な電子顕微鏡写真に刺激を受け、焦りを感じながらも何とか自分なりの美意識を満足させることのできる微細形態の剖出に明けくれた。それは調和のとれた細胞形態・連続性を持った空間の剖出・動的平衡を維持した自然な形態の再現、そこに真実を求める日々が続いた。自然な曲線を描いた脂質二重層からなる細胞膜に囲まれた細胞、局在する様々な形態を示す細胞小器官とそれらの相互的位置関係は、細胞の機能をイメージさせ、連続する細胞外基質や隣接する細胞との微細な構造はさらに組織としての、あるいは器官としての機能を訴えかけてくれた。
確かな方法論に基づいた手法によって得られた微細形態の美しさ、「極美の世界」を手にした時「美は真なり、真は美なり」の持つ意味が実感され、一層豊かなイメージを斯き立てられた。
その後約半世紀に亘り、10年一日のごとく電子顕微鏡の蛍光板上に去来する幻影を追う日々が続いたが、そこに現れては消えて行くうたかたの中には生命の謎や、譬えようもない自然の美しさが秘められており、語りかけによっては実に多くの素晴らしい事実を教えてくれた。しかし、頑なに立ち入ることを拒む自然の厳しさもまた身にしみて感じることもしばしばで、そのような喜怒哀楽の反復こそが研究に対する意欲を培ってきたような気がする。
日進月歩で急速に発展し続けた細胞微細形態学は、固定法・樹脂包埋法・超薄切片法の改良、各種染色法の開発、酵素・免疫組織化学、ラジオオートグラフィーの導入など目まぐるしく進歩し、さらには、高分解能走査電子顕微鏡や元素分析電子顕微鏡の開発・応用などにより急速な発展を遂げた。振り返ると1960-1980年代は正に電子顕微鏡の揺籃期でもあり、また黄金時代でもあった。今となっては、超薄切片を作成するために古いガラスを集め、ガラスナイフを作るために研究室の片隅で日夜ガラスを割り続けていた日々が懐かしく思い出される。
新潟大学歯学部へ移籍した直後、丁度大学紛争の起こる直前1967年、幸いにも米国・テネシー州ナッシュビルのバンダービルト大学、分子生物学研究室Lipid Reserch Lab(Prof.Sidny Fleisher)へ留学する機会を得、ゴルジ体の単離やミトコンドリア内膜の再合成に関する研究に従事し、ロックフェラー研究所のPalade教授とも葉緑体の単離とその呼吸に関する研究などを行う機会が持てた。この留学で分子生物学と微細形態学とのダイナミックな連携の重要性を実感できたことは、その後の私の形態科学にとっても、研究組織の構築・運営などにとっても貴重な体験であった。
骨や歯など硬組織の電子顕微鏡による超微細形態研究に取り組んだのは米国留学を終えて帰国した1970年以降で、当時すでに我が国では歯や骨の超薄切片による微細形態は田熊庄三郎先生を中心に世界的な研究成果が挙げられつつあった。また、骨代謝研究分野では、大学クラスメイトであり良きき友である須田立雄先生がVit Dの研究で優れた研究成果を挙げて活躍しており、同じ大学のキャンパスには骨形態計測のリーダーとして高橋榮明先生がおられたことなどは、私にとっての新しい研究分野である硬組織微細形態学への参入には幸いであった。
硬組織研究はエナメル質・象牙質形成など歯の発生・形成からスタートし、硬組織石灰化機構に関する研究、更には骨代謝機構の研究へと及んだ。
硬組織の微細形態学的解析には、一般的に脱灰法により軟組織とほぼ同じ手法で微細形態を観察するが、硬組織特有のミネラルや結晶の局在や動態を電顕レベルで検索することは不可欠な研究であり、非脱灰観察はもとより、結晶・ミネラルを固定し流失を防いで可視化するための様々な細胞化学的な方法が模索された。その結果、多くの状況証拠を得ることはできたが、直接ミネラルを観察するためには不十分であり、試料作成の全ての段階をanhydrousな条件で行う方法が求められた。当時、神経組織など軟組織で用いられるようになっていた、液体窒素・ヘリウムによる急速凍結・凍結置換法や凍結超薄切片法が最適な方法として硬組織に導入されたのは必然であった。極めて困難な技法を伴うこの急速凍結技法を最初に硬組織研究に用いたのは、ベルン大学のHantikerらAssenciの研究グループと我々であった。この方法によって得られた硬組織の微細形態は、結晶構造の維持のみならず、Ca・Pなど可溶性ミネラルの保存も可能にするとともに、一般軟組織の場合と同様、細胞の微細形態はもとより細胞外基質の形態も従来の化学固定では観察することのできない自然な調和のとれた超微細形態の観察を可能にした。この方法の導入によりミネラルの流出・移動が最小限にとどめられるため、新しく開発された分析電子顕微鏡(EDX,EELS)による元素分析も可能な手段の一つとなった。特にEELSは10―29gという微量元素のマッピングが可能な電子顕微鏡で、一連の石灰化機構解析には必須の機器であった。これら一連の研究は、石灰化機構を始め、硬組織形成・破壊などの機構についても多くの新たな情報を発信し続けることができた。一枚の急速凍結超薄切片を作成するために、その方法の模索とともに、そこに展開する新たな世界を夢見ながら忍耐強くミクロトームと向き合った日々も今となっては懐かしい思い出となっている。
このように、硬組織の形態学的研究はその「硬さ」故に一般の軟組織に比べ、方法論的に多くの困難が伴った。「方法論の進歩は科学の進歩にほぼ一致する」ことは良く知られているが、硬組織の微細形態学的研究はまさに方法論との戦いでもあり、そこには多大な知恵と工夫、たゆまぬ努力が求められた。
「生物学的石灰化機構の解明」は、細胞の微細形態を専攻してきた私にとって大変魅力的な研究課題であった。何時、何処で、如何にしてミネラルが沈着し結晶化して硬い組織を形成するのか、細胞の果たす役割・細胞外基質における結晶化の過程など石灰化の研究は、1923年、Robisonのアルカリフォスファターゼ説、1950年代に出されたNeumannらによるエピタキシー説などが有力な説であったが何れも必要十分とはいえず、それぞれ自家撞着を含んだ説でもあった。
1967年にはBonucchi, Andesrson らにより細胞外基質に存在する細胞膜によって囲まれた小さな小胞「基質小胞」の存在が明らかにされ、その小胞がカルシウムやリンなどのミネラルを集積し、結晶化を開始するという「基質小胞説」が石灰化機構の説として新たに加わった。
私が石灰化の研究に参入した時期は、丁度基質小胞説が微細形態学的所見をもとに新しい学説として注目され始めた時期に一致し、我々も「基質小胞」について、あらゆる硬組織形態学的手法を駆使して研究を進め、各種硬組織をはじめ比較解剖学的にも、病的・異所性石灰化部位にも普遍的に存在すること、さらにその細胞化学・物理学的特徴についても石灰化機構との関連性を明らかにしてきた。 特に急速凍結手法・微小部元素分析法により、石灰化開始部位における有機基質の微細形態的特徴、石灰化開始部位におけるミネラル集積機構、結晶析出制御機構を担う有機性結晶鞘の解析、コラーゲン細線維に対するヒドロキシアパタイト結晶沈着機構の解明などについての研究を重点的に行った。
我が国では、1972年の国際細胞化学会における基質小胞の細胞化学的研究が注目を浴び、次いで1975年の第10回国際解剖学会で主催した「硬組織シンポジウム」を通してようやく「基質小胞性石灰化」は人々の関心を集めるようになった。さらに、1983年第8回国際カルシウム調節ホルモン(ICCRH)のサテライトシンポジウムとしてC.Anderson,E.Bonuci,Y.Aliらmatrix vesicle の中心的研究者を招いて”Cell-mediated calcification-Matrix Vesicle”を新潟で主催し、基質小胞性石灰化についての認識と理解を高めることができた(付図)。
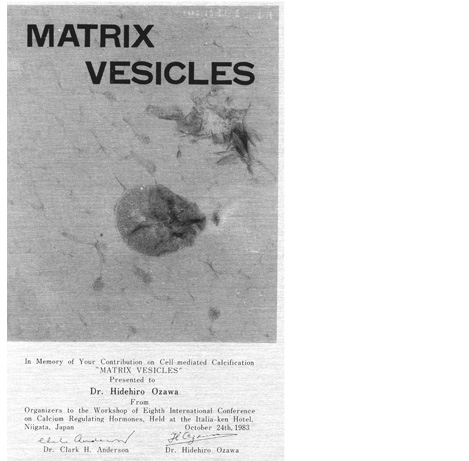
Cell-mediated calcification Matrix Vesicles のポスターのコピー
生物学的石灰化に関してはその後、2000年に8th International Symposium on Biomineralizationを新潟で主催し、下等生物から哺乳類にいたるまで基質小胞性石灰化を含め広く生物学的石灰化現象を討議したことはまだ記憶に新しい。
基質小胞性石灰化に関してはその後多くの研究が蓄積され、基質小胞は少なくとも石灰化開始部位における石灰化開始時期・機構・量の決定については必須であると考えられている。しかし現在なお、その分泌・形成機構については明確な結論が得られていない。発芽様・マイクロアポクリン様分泌、exocytosis(exosome)、細胞死による全分泌など様々な説があるが、何れも確かな電子顕微鏡レベルの裏付けがないのが現状である。今後一層確かな微細形態の検索とともに分泌時期・部位特異性とも関連して遺伝子レベルでの解析が待たれるところである。
このように基質小胞については1967年始めて電子顕微鏡でその存在と形態が明らかにされて以来、紆余曲折しながらも漸く定説化した感があるが、どの学説でもそうであるように定説化していたコラーゲン学説に異議を唱えることは至難の業であり、当初「基質小胞性石灰化説」は一時異端扱いされたことを今でも記憶している。「あれはゴミである!」との耐え難い評価を受けたことすらあった。正に、レッドヘリング現象であり、「燻製イワシを見て、イワシは赤い」と信じている人々には「黒いイワシ」は存在しなかったのであろう。形態学に限らず研究には時として自分に都合の良いものだけ、あるいは自分に分かるものだけみていることがある。意図しているわけではないが結果としてすでに概念化された所見以外は見ていない。すなわち、意識しないと見えてこない、視的意識visual consciousnessの問題があり(朔 敬)、基質小胞の発見の遅れもその一つであったのだろう。また、他の研究分野でも起こりうることであるが、電子顕微鏡の醸し出す「極微の世界」では特に、鋭い感性・感受性を持って見つめればそこには必ずselendipity「思いがけない発見」が待ち構えており、基質小胞の発見もselendiptousであったのかもしれない。
一方、骨代謝研究では、須田立雄先生、久米正好先生らと破骨細胞を囲んで喧々諤々と渡り合った日々などが懐かしく思いだされる。
骨芽細胞の破骨細胞分化・活性化への役割、骨吸収と骨形成のカップリング現象の微細形態学的・細胞化学的所見、骨細胞の形態と機能、特に破骨細胞分化に対する骨細胞の重要性、腫瘍性骨吸収とその抑制機構など多岐に亘る研究を電子顕微鏡はじめ共焦点レーザー顕微鏡、μCTなど各種の形態観察機器を駆使して用いて研究を進め、in vivoでの骨代謝について形態学的知見を発信し続けた。近年、クライオTEM、大気圧走査電顕ASEM、FIB-SEM、ラマン分光イメージングなどによる多角的な検索とともに、多光子・2光子レーザー顕微鏡などの開発によりin vivoでの細胞動態の「動的」観測も可能になり、骨代謝形態科学は新たな展開を見せている。
飛躍的な発展を遂げつつある近代生物学や生命科学は、まだ氷山の一角を現したに過ぎない。
しかし、この半世紀の間に確立された生物学、生命科学に関する知識量は、それまでの人類の歴史の中で築き上げられた知識量をはるかに凌駕し、人類の存在感すら大きく変化させようとしている。
そしてこのような科学の急速な進歩は、それぞれの分野の細分化を招き、専門外の人々との間に一見大きな溝を作り始めた感があったが、共通語による統一も促され、生命科学は急速に統合化され新たな展開を見せている。このような科学の潮流であればこそ、形態学研究者には、より一層トポロジカルに「形」を正しく捉え、正しく「形」を読む感性を磨き、細分化した科学を統合し予見するする役割が求められている。
ポストゲノム時代の今日であればこそ、まさに“形態科学への「回帰」が生じており、形態に織り込まれた生体情報を抽出、再構築する要の学問としての形態科学が見直される「ルネサンス」の機運が高まっている”とする植木 孝俊氏(解剖学雑誌90:11,2015)の主張にも改めて耳を傾けたい。
昨今、人工頭脳AI(Artificial Inteligence)の進化が止まらない。AIは物事を学習し、考える能力を持たせたコンピューターのプログラムだ。AIが囲碁の日中韓トップ棋士と争ったワールド碁チャンピョンシップで日本の井山祐太6冠を下し、昨年は韓国人棋士が別の囲碁ソフトに1勝4敗と負け越している。また、ロボットが支配する星を描いたウルトラセブンの「第四惑星の悪夢」にはこんなセリフがある。「人間は我々ロボットを生み出してから、すっかり怠け者になってしまって、ロボットにとって代わられたというわけだ」(新潟日報:2017・3・29)
まさに、コンピューターの進歩は今や人類の存在すら脅かそうとしている。寡ってアメリカへ留学した折、1969年にナッシュビルで「2001年宇宙の旅」の映画を見たが、宇宙船に搭載されたコンピューター・ハルが反乱を起こす場面を見たときの驚きを今でも覚えている。ハルはHL: Heuristically programmed Algorithmic Computer「発見的なプログラムを施されたアルゴリズム・コンピューター」を意味するらしく、何れ人類と同様あるいはそれ以上の感性・想像力をもって地球を支配する可能性をすでに当時予見した映画だった。このような世界の実現が現実化しようとしている現在、生命科学はどのような発展を遂げるのだろう。とりわけ進化したAIが、形態を如何に読みイメージし、さらに定量化してそこから新たな情報を発信するか、楽しみと一抹の不安を感じるこの頃である。
半世紀にわたり形態科学と取り組んできた私は、この間良き師・ 先輩そして良き研究仲間との纏綿とした出会いがあり、この出会いこそが私の人生の宝と感謝している。特に多くの大学院生・研究仲間を得、それぞれ優れた硬組織研究者・教育者として活躍し、現在なお活発に硬組織形態科学の研究を進めていることは、厚かましいとは思いながらも伯楽冥利に尽きると感じているところである。
稿を閉じるにあたり、中島友紀教授には脱稿が大変遅くなりご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げるとともに、このような機会を与えて頂きましたことに感謝して稿を閉じたい。
参考文献
小澤 英浩:一筋の硬組織形態学研究への歩みー硬組織形態科学の復権を目指してー、日骨代謝誌 18(1):1,2000
小澤 英浩:骨の超微細形態学研究の流れ、The Bone 20(5):21,2006
小澤英浩:わが国の骨代謝研究20年のあゆみ、The Bone 20:135,2006
小澤 英浩:医想 “極微の美に魅せられて” Pharma Medica 26(1): 5, 2007